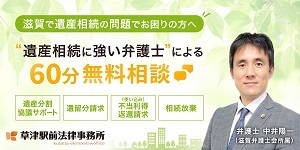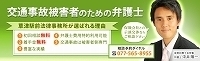滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
現在当事務所の業務が非常に立て込んでいるため、当面の間新規のご相談予約受付を停止しております。
ご不便をおかけしますがなにとぞご了承ください。
子の面会交流の相場
面会交流の頻度・回数・時間などについて相場はありますか?
年齢や子どもとこれまでの親子関係等にもよりますが、月1回が基本で、長期休みの際に宿泊を伴う交流が認められることがあります。

まだ離婚をしていなくて別居中の場合でも、離婚をした後であっても、子どもを監護していない側の親は、子どもの福祉に反しない限り、子どもと面会交流をする権利があります。
面会交流の頻度や回数・時間については、当事者間(父母)の協議で決めるのが原則です。
しかしながら、協議で決まらない場合には、家庭裁判所の調停や審判で決めていくことになります。
家庭裁判所の調停や審判で決まる際の、頻度や回数・時間についての相場ですが、それまでの親子関係や、子どもの年齢によって様々です。ただ、おおざっぱに言うと、「月1回」が基本となることが多いです。
時間については、小学校入学後以降ですと、ほぼ1日(10時頃~17時頃など)であったり、半日というケースが多いように思われます。他方で、まだ未就学児の場合、時間が短くなるケースがあり、特に乳幼児の場合には、2時間程度に限定されたり、母親の付き添いを認めるケースも見受けられます。
また、小学校入学以降の場合、非監護者と子どもの関係がそれなりに良好で、非監護者が希望すれば、夏休みなどに宿泊を伴う面会交流が認められることもあります。
いずれにしても、明確な基準や相場があるわけではありません。お子さんと非監護者とのこれまでの関係性や面会状況、お子さんの意思や年齢によって、個別具体的に判断されることになります。
なお、子どもが中学校入学後以降になると、お子さんの意思が最優先される傾向があります。もっとも、母が「子どもが会いたくないと言っている」と主張をしても、父が「母が言わせているだけだ。子どもは喜んでいる」と反論するケースがよくあります。
調停や審判でそのような争いになった場合には、家庭裁判所調査官という専門官が、お子さんと直接会って、お子さんの意向を確認するという手続が行われることが多いです。
初回無料法律相談予約はこちら
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
当事務所関連サイト
離婚知識について詳しく解説したホームページです。
遺産相続問題について詳しく解説したホームページです。
交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。