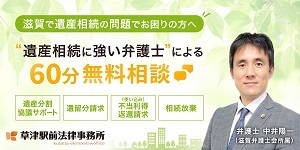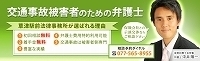調停とは、中立な立場の調停委員が当事者の間に入り、双方が直接顔を合わさなくても紛争の話合いができるという裁判所の制度です。
特に、家事事件と呼ばれる離婚や相続の問題については、「調停前置主義」と言って、いきなり裁判等をするのではなく、まずは調停を申し立てなさいと法律で決まっているものが多いです。
通常の民事裁判ですと、裁判所はあくまで書面中心主義で、主張書面と証拠を元に結論(判決)に向けて進めることになります。通常の民事の裁判期日も約10分程度と非常に短いです。
他方で調停の場合、調停委員が各当事者の話をじっくりと聞いて調整をするため、調停期日は元々約2時間程度(場合によってはもっと長時間)の時間をとっていました。
もっとも、最近では調停においても合理化の波が押し寄せており、大津家庭裁判所の場合、調停時間は原則として最長80分間とされています。
80分と言っても、当事者が調停委員と話す時間だけではなく、途中で調停委員と裁判官の評議の時間や、当事者が調停室と待合室を行き来したりする時間もかかるため、そうすると当事者が調停委員と話をする時間は1人あたり30分くらいしか取れません。
時間が十分に取れない → 話をしっかり聞いてもらえない → 当事者に不満が募る
という悪循環が生じてしまう気がするのですが、これも時代の流れで仕方ないものなのでしょうか。
執筆者:弁護士 中井陽一 最終更新日:2025年2月25日